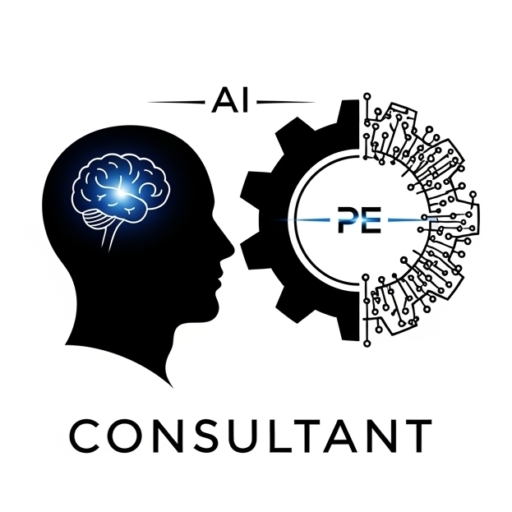技術士二次試験(建設部門)論文の書き方
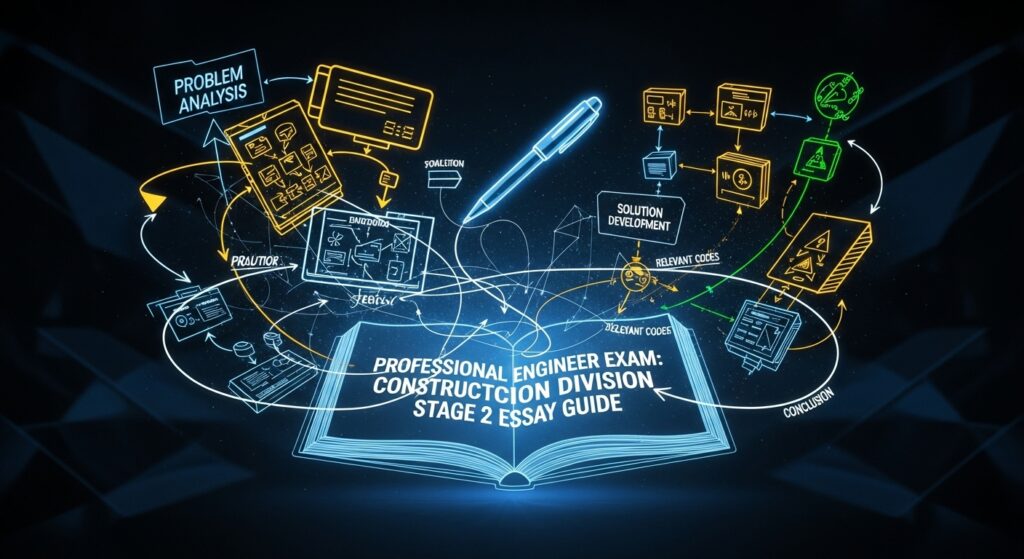
こんな方へ
- 記述試験(必須Ⅰ・選択Ⅱ・Ⅲ)の**採点観点(コンピテンシー)**を踏まえた“勝てる型”を身につけたい
- 問題文のキーワードを取りこぼさず、答案に反映するコツを知りたい
- 自分の業務経験を、題意に沿って筋の通った骨子に落とし込みたい
試験の全体像
- 形式:すべて記述式(600字詰×3枚/1,800字以内)
- 科目:
- 必須Ⅰ…技術部門全般(専門的学識/問題解決/評価/技術者倫理/コミュニケーション)
- 選択Ⅱ-1…専門知識(“定義・分類・留意点”などを1枚で一覧化)
- 選択Ⅱ-2…応用能力(調査項目→手順→関係者調整)
- 選択Ⅲ…問題解決(Ⅰの①〜③から倫理を除いた構成が基本)
- 合否:各問題で**6割以上(A評価≥60点)**が目安
合格のポイント
① コンピテンシーの理解と各問題への落とし込み ⇒ 論文の型の習得
コンピテンシーは、受験案内および評価の観点(採点基準)に明記された評価軸です。建設部門では、①専門的学識、②問題解決、③マネジメント、④評価、⑤コミュニケーション、⑥技術者倫理の六つを中核として、答案の内容と構成がこれらの観点から総合的に判定されます。
また、設問ごとに重視されるコンピテンシーは異なります。必須Ⅰは、設問1・2で問題解決(あわせて専門的学識・コミュニケーション)、設問3で評価(連続する論理の整合)、設問4で技術者倫理が中心です。選択Ⅱ‑1は専門的学識とコミュニケーション、選択Ⅱ‑2は専門的学識・マネジメント・コミュニケーション(現場のリーダーシップを含む)が問われ、選択Ⅲは専門的学識・問題解決・評価・コミュニケーションの四点が主対象となります。
コンピテンシー一覧
- 専門的学識:法令・制度、社会・自然条件、最新施策を“理解して応用”
- 問題解決:①問題発見→②原因分析→③課題設定→④対策立案の連鎖
- マネジメント:QCD(品質・コスト・納期)とリスク管理
- 評価:効果・限界・波及・新たなリスクの見通し
- コミュニケーション:読みやすさ(入れ子・短文・箇条書き)
- 技術者倫理:公益(安全)最優先/持続可能性(環境・社会)
設問別に対応するコンピテンシー
- 必須Ⅰ
- 設問1(課題抽出):問題解決+(専門的学識・コミュニケーション)
- 設問2(方策提起):問題解決+(専門的学識・コミュニケーション)
- 設問3(新たなリスク・評価):評価+(問題解決の連続性)
- 設問4(倫理・持続可能性):技術者倫理
- 選択Ⅱ-1(専門知識):専門的学識+コミュニケーション
- 選択Ⅱ-2(応用能力):専門的学識+マネジメント+コミュニケーション+リーダーシップ
- 選択Ⅲ(問題解決):専門的学識/問題解決/評価/コミュニケーション(倫理は通常不要)
設問別のコンピテンシーを網羅するための論文構成
必須Ⅰ(2時間)
- 【設問1|課題抽出】現状→原因→課題
- 【設問2|方策提起】最重要課題=◯◯(理由)→解決策A/B/C(解決策の概要、解決策の効果、具体例)
- 【設問3|新たなリスク】(共通)二次/残留リスク→対策
- 【設問4|倫理・持続可能性】公益最優先/環境・地域配慮
選択Ⅱ-1(1枚完結):問題文で求められている事項を網羅(一覧性重視)
選択Ⅱ-2(3設問):設問の要求事項通りに業務計画書を作るイメージで、**調査・検討項目:**キーワードが網羅できるように、マニュアルやガイドラインの内容を記載
選択Ⅲ:Ⅰの1〜3を踏襲(倫理は除外)
書き方の技術(=コミュニケーション能力)
- 入れ子構造(章→節→項)
- 1文60〜100字、箇条書き多用
- 用紙配分:Ⅰは設問均等、Ⅱ-1は版面バランス
② キーワードの網羅 ⇒ 国のマニュアル等のキーワードを論文に落とし込む
キーワードを“取りこぼさない”技法
受験部門のキーワードを抽出し、そのキーワードを手掛かりに、自分の専門分野に関する問題点・課題・解決策・リスクを漏れなく洗い出す。 そのうえで、抽出結果を試験の設問構成(Ⅰ-1:問題/課題、Ⅰ-2:解決策、Ⅰ-3:新たなリスク)に対応づけ、論理の流れの中へ自然に落とし込めるようにする。この一連の流れを確実に回せることが重要である。
③ 問題文(前提条件)の強い意識 ⇒ 前提条件に基づく問題・課題・解決策
前提条件の読み解き→構成への“紐付け”
前提条件には、答案に必ず盛り込むべきキーワードのヒントが隠れています。対象地域(都市部/地方部/半島部 等)、対象事象(地震・津波・土砂災害 等)、数や範囲の指定(「3つ」「全国でなく地方部」など)、そして時制(発災直後→応急→復旧・復興)といった記述を丁寧に読み解くと、何を軸に課題を整理し、どの語を見出し・本文に出すべきかが自ずと定まります。
具体例①:R7年度都市及び地方計画からの出題
R7試験では、日本海側の半島部で地震が発生した場合の復興対策に関する技術課題が問われました。この前提は「全国一般論」ではなく、地方部かつ半島部という地理的制約を強く示しています。したがって、能登半島地震で顕在化した複合災害(大規模地震+洪水)に触れ、それらに由来する具体的な技術課題を明記することが肝要です。
さらに、受験部門が「都市及び地方計画」なので、災害リスクを踏まえた“住まい方”(居住誘導・土地利用・移転含む)に言及することが必要です。例えば、ハザードに応じた居住誘導(コンパクト+ネットワーク)、防災集団移転や高台移転、地域公共交通のレジリエンス確保、生活圏再編と生活復興の段階設計(応急→仮設→恒久)などを政策語とともに示すと、部門の特性に合致した答案になります。
具体例②:R7年度建設部門必須
今年度の建設部門「Ⅰ-2」では、社会資本重点計画の三つの抽象的な目標(「国民の安全・安心の確保」「持続可能な地域社会の形成」「経済成長の実現」)が提示され、そのうち**「経済成長の実現」**に言及があります。したがって答案は三目標を網羅するのではなく、経済成長に論点を絞って構成することが求められます。
加えて、問題文には観光の活性化、製造業等の国内回帰・集積の見直し、DX/GXによる成長産業の構造転換への対応など、具体例が記載されています。これらに直結する、問題点→解決策→成長への寄与→新たなリスクを整理します。
Point:ここで、自分の学習した内容を問題文を踏まえずそのまま書いてしまい、減点されている例が多いです!
例1|観光立国の推進(経済成長×交通)
- 問題点:空港・港湾・主要駅と周辺観光地を結ぶ二次交通の脆弱、広域周遊を阻む交通結節点の不足・乗継不便、都市部と地方の集客偏在。
- 解決策:空港・港湾・新幹線/主要駅を核とした交通結節点の整備(同一フロア乗継・動線短縮・多言語案内・IC/QR一体化)、鉄道・バス・LRT・コミュニティ交通のダイヤ連携と広域MaaSによる一体的チケット、主要観光地間の観光回遊ルート設定と周遊パス導入。
- 期待効果(インバウンドの全国回遊):地方分散・滞在日数と消費単価の増加・再訪率向上。
- 新たなリスク:観光公害・交通混雑・投資回収リスク→需要平準化(時間帯/季節分散)とDMO連携マネジメント、公共交通の運行確保(運転士確保・増便の段階実施)で抑制。
例2|物流・サプライチェーンの強化(経済成長×交通)
- 問題点:高速道路・高規格幹線道路や主要地方道におけるミッシングリンクの残存、慢性的な隘路(車線・幅員不足、急カーブ・急勾配、踏切・平面交差)、都市圏のボトルネックによる所要時間の不確実性。
- 解決策:高規格道路ネットワークの連結(未整備区間の早期整備、BP・IC追加、環状道路の整備)、ボトルネック解消(4車線化・立体交差化・左折レーン増設)、災害時の代替ルート確保(広域迂回路・緊急輸送路指定の見直し)等、道路整備の重点化と計画的実施。
- 成長への寄与:物流リードタイム短縮・定時性向上によるサプライチェーン強靭化、観光・産業立地の促進、地域間交流の活性化。
- 新たなリスク:環境負荷・沿道影響、事業費増大・用地調整の難航、需要予測の不確実性→環境配慮(GI・騒音/大気対策)、B/C・段階整備、合意形成の早期着手で対応。
学習ロードマップ(4ステップ)
上記を踏まえ、以下の学習ロードマップが有効と考えます。
- 重要テーマを絞る(社会資本重点計画・白書など)
- 知識(キーワードの理解)を蓄積(白書→省庁資料→専門誌で深掘り)
- ロジック構成(①問題→②分析→③課題→④解決策→⑤新リスク)
- 文章化(テンプレに流し込み→音読推敲)