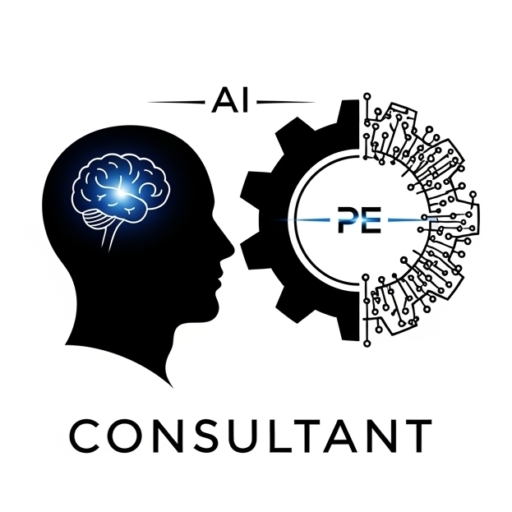技術士2次試験対策
技術士二次試験の合格には、体系的な知識と適切な論文作成スキルが不可欠です。長年の指導実績に基づいた試験対策情報を発信するとともに、合格に向けた実践的なサポートを提供しています。技術士二次試験の突破に向けて、私たちが全力でサポートいたします。
学習支援アプリ
効率的な学習をサポートする専用アプリで、いつでもどこでも試験対策が可能です。
論文サンプル
合格レベルの論文例を多数掲載。書き方のポイントや構成を具体的に学べます。
論文添削サービス
経験豊富な技術士による丁寧な添削で、あなたの論文を合格レベルへ導きます。
模擬面接(口頭試験対策)サービス
経験豊富な技術士による模擬面接で、あなたを合格レベルへ導きます。

試験概要
- 技術士第二次試験は、第一次試験合格者などの受験資格を有する者が、いずれか1つの技術部門を選択して受験します。
- 試験は筆記試験および口頭試験で構成され、実務に基づく専門性・応用力・問題解決力・倫理観等が総合的に評価されます。
- 筆記合格者のみが口頭試験へ進み、両方に合格すると技術士として登録可能になります。
メリット
管理技術者になれる
- 国、自治体の案件では、プロジェクトマネージャーの要件として技術士が求められます。
- 管理技術者は案件形成からプロジェクトのデリバリーまですべてを管理する立場になりますので、個人の実績・対外的なPRに活用できる。
建設コンサルタントの場合、管理職の要件
- 多くの企業で課長級以上の昇格要件に技術士が求められます。
- 管理技術者実績が評価・処遇拡大に直結します。
転職有利に建設コンサル⇒総合コンサルで年収アップ可能
- PM実績を武器に総合コンサル等へ転身し、年収・役職の上振れを狙える。
- わたしの転職の際も、技術士資格と管理技術者経験が評価され、年収UPを実現できました。
技術士手当
- 登録保有者に技術士手当が支給される場合があります。
- 前職では毎月6000円+一時金20万でしたが、他社では月5万円UPの会社もありました。
難易度(合格率)
- 直近の公表値(令和6年度実績・対受験者)で合格率はおよそ10%台前半(例:10.4%)。
- 部門により差があり、例として建設系は一桁台後半〜10%台前半、総合技術監理部門は相対的にやや高めの傾向。
- 年度により変動するため、正式な最新値は日本技術士会の公表資料をご確認ください。
受験資格
一次試験合格またはJABEE修了の修習技術者が対象。
実務経験は3経路:
- 技術士補として、指導技術士の下で4年以上(※総合技術監理部門は7年以上)
- 職務上の監督者の下で4年以上(※総合技術監理部門は7年以上)
- 7年以上の実務経験(※総合技術監理部門は10年以上)
※大学院は最長2年加算可/技術士補登録は必須ではありません。
試験の構成
(A)総合技術監理部門を除く各技術部門
- 筆記試験(必須・選択)
- 部門全般に関する専門知識・応用力・問題解決・課題遂行を問う記述式中心。
- 設問は「全般(必須)」と「専門知識/応用能力/問題解決・課題遂行」で構成。
- 口頭試験
- 実務経験に基づく説明能力、コミュニケーション、リーダーシップ、評価・マネジメント、倫理・継続研さんなどを総合的に確認。
(B)総合技術監理部門(総監)
- 筆記試験(必須):択一+記述を組み合わせ、技術に関わるマネジメント(QCD、リスク、資源配分、合意形成等)を体系的に問う。
- 筆記試験(選択):上記(A)と同様に専門知識/応用/問題解決を掘り下げて記述。
- 口頭試験:経歴・応用能力・体系的専門知識などを中心に質疑応答。
コンピテンシー
- 専門的学識:部門全般と選択分野の知識を、制度・社会・自然条件も踏まえて理解・適用できる。
- 問題解決:複合課題の把握、要因分析、相反要件の整理、実行可能で合理的な解決策の提示。
- マネジメント:品質・コスト・納期・生産性・リスク等に対する資源配分・評価・改善。
- コミュニケーション/リーダーシップ:関係者との合意形成、チーム運営、説明・記録能力。
- 技術者倫理/継続研さん:公益性・安全性・説明責任を重視し、最新知識を継続的に獲得。
求められるスキル
- 論述力と論理構成力:設問意図を外さず、制限字数内で要件を満たす明快な構成(序論→本論→結論・提言)。
- 専門知識の幅と深さ:重要キーワード・最新トピックの理解と、自身の業務への適用・検証。
- 問題解決設計力:課題抽出→分析→代替案設計→評価→実行計画(体制・工程・リスク対策)までを一貫提示。
- マネジメント実務感覚:QCD・安全・リスク・コンプライアンスを踏まえた現実的な判断と改善提案。
- 対話力・説明力・倫理観:口頭試験での要点提示、質疑応答、根拠の明示、ステークホルダー配慮。
- 継続学習力:業務・学会・技術情報からのインプットと、実務でのアウトプット(ナレッジ化)。
※ 合格率・配点・設問構成等は年度により変更される場合があります。最新情報は日本技術士会の公式資料(受験案内・試験結果・採点基準等)をご確認ください。