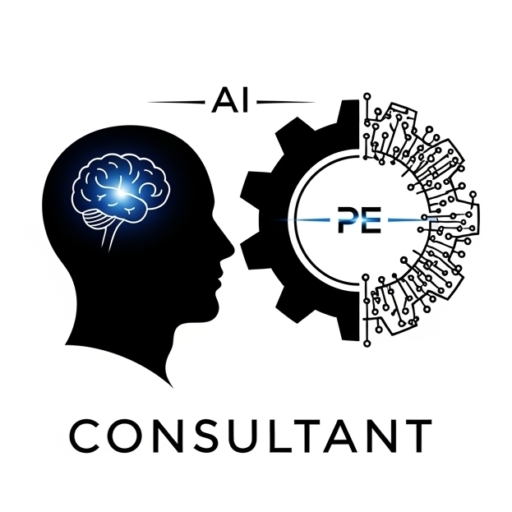口頭試験対策
技術士第二次試験における口頭試験は、筆記試験を通過した方に対して「技術士として独り立ちできるだけの資質と実務力が備わっているか」を確認する最終ステージです。試験官(おおよそ2~3名)との対面で行う面接方式で、1人あたりの時間はおおむね20分前後です。
質問は、筆記試験の内容や提出した業務経歴をもとに進められます。単に知識を問うのではなく、
- 関係者と連携しながら仕事を進める力(コミュニケーション・リーダーシップ)
- 業務を計画し、段取りを組み、成果を取りまとめる力(評価・マネジメント)
- 公益や安全・環境へ配慮した判断ができているか(技術者倫理)
- 継続的に学び、能力を高めていく姿勢(継続研さん)
といった観点から、「どのような考え方で仕事に向き合っている技術者なのか」を総合的に見られます。
その際、
- どのような背景や制約の中で業務に取り組んだのか
- どの立ち位置・役割で、どのように周囲を動かしたのか
- どのような工夫・判断を行い、その結果どうなったのか
- そこから何を学び、次にどう生かしているのか
といった点が、主な確認対象となります。
2.口頭試験に不合格となった場合
口頭試験は、技術士第二次試験の最終ステップです。ここで不合格となった場合、その年度の第二次試験は不合格となり、翌年度以降に再挑戦する際には、再度「筆記試験から受験し直し」となります(口頭試験だけを受け直す制度はありません)。
そのため、筆記試験に合格した段階で安心してしまうのではなく、「口頭試験こそ本番」という意識で、早い時期から準備を始めることが重要です。
3.不合格となりやすいケース
口頭試験で不合格となるケースには、いくつか共通した傾向があります。代表的なものを挙げると、次のようなものです。
(1)準備不足・場当たり的な受験
- 業務経歴票の内容を自分の言葉で説明できない
- 想定される質問に対する答えを整理できていない
- 最新の技術動向や関連制度をほとんど把握していない
こうした場合、質問に対して回答がちぐはぐになったり、沈黙が続いたりし、技術士としての専門性・信頼性に疑問を持たれてしまいます。
(2)コンピテンシーの視点が不足している
- 「自分がどんな作業をしたか」の説明だけで終わってしまい、
・問題解決のプロセス
・品質・コスト・納期やリスクのマネジメント
・関係者との調整やリーダーシップ
・成果の評価や次への改善
といった視点が示されていない
筆記・口頭ともに、「技術士に求められる資質能力(コンピテンシー)」に基づいて評価されるため、単なる作業の羅列や技術用語の暗唱だけでは、評価が伸びにくくなります。
口頭試験で特に意識しておきたいコンピテンシーは、次の8項目です。ここでは、公式な文言ではなく、受験対策として押さえておきたいイメージに言い換えて整理しています。
- 専門的学識:自分の専門分野について、基礎から応用まで筋道立てて理解しており、実務の場面でその知識をきちんと使いこなせること。
- 問題解決:現場で起きている課題の背景を整理し、原因を分析したうえで、いくつかの選択肢を比較検討しながら現実的な解決策を組み立てていく力。
- マネジメント:品質・コスト・スケジュール、さらにはリスクや安全面のバランスを考えながら、業務の進め方を計画し、関係者と調整しつつやり遂げる力。
- 評価:自分たちの行った仕事の良かった点・足りなかった点を客観的に振り返り、数字や事実を踏まえて整理し、その結果を次の業務改善につなげていく力。
- コミュニケーション:発注者・社内メンバー・住民など、立場の異なる相手に対して、分かりやすい言葉や資料で説明し、合意形成を図っていく力。
- リーダーシップ:自分が前に立つ場面だけでなく、状況に応じて周囲を支えたり背中を押したりしながら、チームとして目標達成に向けて動かしていく力。
- 技術者倫理:法令や基準に従うのはもちろんのこと、公益・安全・環境への影響を踏まえて「技術者としてどう判断し、どう行動するか」を自ら考え、実践する姿勢。
- 継続研さん:日々変化する技術や制度に取り残されないよう、研修・学会・自己学習などを通じて学び続け、その成果を実務に還元していこうとする姿勢
口頭試験では、これらのコンピテンシーの定義に沿って、自分の業務経験をどのように説明できるかが重視されます。「何をしたか」に加え、「どのコンピテンシーをどのように発揮したのか」を意識して回答することが、合格への近道となります。
(3)技術者倫理への意識不足
- 安全よりもコスト優先の発言
- 法令や基準への遵守姿勢が曖昧
- 不具合発生時の対応や報告の仕方が不適切
倫理に関する質問で判断を誤ると、大きな減点要因となり、不合格につながりやすくなります。
(4)コミュニケーション面での課題
- 質問に対して直接答えず、論点がズレる
- 話が冗長で要点が分かりにくい
- 早口・小声・落ち着きのなさなどで、内容が伝わりにくい
口頭試験では、「正しい内容を、限られた時間で分かりやすく伝える力」も評価されています。
4.合格するための対策
口頭試験を突破するためには、「思いつきで話す」のではなく、コンピテンシーを意識した体系的な準備が不可欠です。
(1)業務経歴の棚卸しと整理
- 業務経歴票に記載した各業務について、
「背景・目的/自分の役割/技術的な工夫/マネジメント上の工夫(QCD・リスク・関係者調整)/成果と反省・改善点」
を1案件ごとに整理しておきます。 - それぞれの業務が、
「専門的学識」「問題解決」「マネジメント」「評価」「コミュニケーション」「リーダーシップ」「技術者倫理」「継続研さん」
のどのコンピテンシーと結びつくかを意識しておくと、質問に対して一貫性のある回答がしやすくなります。
(2)想定問答の作成(コンピテンシー別)
想定問答は、「聞かれそうな質問を並べる」だけではなく、それぞれのコンピテンシーに対応した内容にしておくことが重要です。口頭試験では、次のような観点ごとに質問されることが多く、それぞれについて自分の業務経験をもとに2~3分で話せるよう準備しておきます。
<専門的学識>
- 質問例:「ご自身の専門分野と、その中で現在重要と考える技術的課題について説明してください。」
- 回答例:「私の専門分野は○○であり、近年は△△の老朽化や需要変化に対応した計画・設計が課題となっています。私は××業務において、□□の指針や最新の技術動向を踏まえた検討を行い、△△の課題に対して耐久性・コストの両面から最適な案を提示しました。」
<問題解決>
- 質問例:「これまでの業務で直面した最大の課題と、その解決のために行った工夫を教えてください。」
- 回答例:「○○業務では、当初の需要予測と実際の交通状況に乖離があり、計画案の見直しが必要になりました。私は、追加調査によるデータの再整理と、複数案の検討・比較を行い、関係者と協議しながら最終案を合意形成しました。この中で、課題の原因分析と代替案の比較検討を丁寧に行ったことが、問題解決につながりました。」
<マネジメント>
- 質問例:「品質・コスト・工程(QCD)やリスクへの対応で工夫した点を教えてください。」
- 回答例:「○○業務では、調査・検討・関係者協議が限られた期間に集中していました。私は工程表を細分化し、重要なマイルストーンごとに成果物とチェックポイントを設定しました。また、リスクとして想定される追加調査や設計条件の変更に備え、代替案を事前検討しておくことで、工程遅延やコスト増加を抑制しました。」
<評価>
- 質問例:「担当した業務の成果をどのように評価し、次の業務にどう生かしましたか。」
- 回答例:「○○業務の完了後、計画案の実施状況や利用状況をフォローアップし、想定どおりの効果が得られているかを検証しました。その結果、△△の効果は想定以上でしたが、一方で□□の課題が残りました。これを踏まえて、次の業務では、評価指標の設定やモニタリング方法を改善し、より定量的に効果検証できるようにしました。」
<コミュニケーション>
- 質問例:「発注者や関係者とのコミュニケーションで工夫した点はありますか。」
- 回答例:「地域住民の不安や疑問が多かった業務では、専門用語を避け、図や写真を用いた資料を作成しました。また、住民説明会では、一方的な説明ではなく質疑応答の時間を十分に取り、意見を整理した上で計画に反映することで、信頼関係の構築に努めました。」
<リーダーシップ>
- 質問例:「チームをまとめる立場として意識した点を教えてください。」
- 回答例:「○○業務では、私が実質的な取りまとめ役として、担当者ごとの役割分担と進捗管理を行いました。メンバーの得意分野を踏まえて担当業務を割り振り、週1回の打合せで課題共有と支援を行うことで、チーム全体としてスムーズに業務を進めることができました。」
<技術者倫理>
- 質問例:「技術者倫理の観点から迷った場面や、特に留意した事例はありますか。」
- 回答例:「○○業務では、コスト縮減案として安全性に影響する可能性のある選択肢が挙がりました。私は、技術基準や過去事例を確認した上で、安全性を優先すべきと判断し、その理由を発注者に丁寧に説明しました。結果として、コストは一定程度増えましたが、安全性と公益性を確保した案が採用されました。」
<継続研さん>
- 質問例:「技術者として、今後どのような継続研さん(CPD)を行う予定ですか。」
- 回答例:「これまで○○分野の業務を中心に経験してきましたが、今後は△△やデジタル技術との連携が重要になると考えています。そのため、学会やセミナーへの参加、専門書・論文の継続的な読書に加え、社内外の勉強会で得た知見を業務に還元することで、自身の専門性を高めていきたいと考えています。」
このように、コンピテンシーごとの質問と回答例を準備し、自分の業務内容に置き換えて2~3分で説明できるよう、要点メモを作成して音読練習しておくと、本番でも落ち着いて話せるようになります。
(3)模擬面接・第三者からのフィードバック
自分一人では「説明の分かりやすさ」や「話し方のクセ」に気付きにくいため、
- 同僚・先輩技術士に模擬面接をお願いする
- 録画・録音して、自分で見返す
などの方法で、第三者視点からの改善点を洗い出すと効果的です。
(4)最新の動向・制度の確認
受験する部門・科目に関連する
- 白書・国の計画・ガイドライン
- 関連法令・基準の改正
- 最近の事故・災害や社会的なトピック
を一通り押さえ、「なぜその施策が必要なのか」「自分の業務とどう関係するのか」を説明できるようにしておくと、説得力が高まります。
5.試験当日の留意点
最後に、当日の受験にあたっての実務的なポイントです。
(1)時間と持ち物の管理
- 受験票・身分証明書(写真付き)
- 試験案内で指定された持ち物一式
を前日までに準備し、会場には余裕をもって到着するようにします。
(2)第一印象と話し方
- 入室時の挨拶・姿勢・身だしなみは、短時間で印象を左右します。
- 着席後は、落ち着いて、聞き取りやすい速度と声量を意識して話すようにします。
- 緊張していること自体はマイナスではありません。深呼吸をし、「相手に伝える」ことに意識を向けるのがポイントです。
(3)質問の意図を確認する
- 質問の意味が分からない場合は、そのまま答えず「〇〇という観点でよろしいでしょうか」と確認してから回答します。
- 質問に対しては、最初に結論、その後に理由・具体例という順序で話すと、短時間でも伝わりやすくなります。
(4)知らないことへの対応
- 知らない事項や経験していない内容を聞かれた際に、推測で答えるのは危険です。
- 「現時点で正確な知識を持ち合わせていないため、帰社後に調査して業務に反映します。その際には〇〇のような観点で確認します。」といった形で、技術者としての適切な対応プロセスを示すことが重要です。
(5)最後まで技術者倫理を意識する
- 公益の確保、安全・安心の確保、法令遵守、環境・次世代への配慮といった観点を常に頭に置き、「技術士としてどう行動するか」を一貫した姿勢で示すことが、合否を分けるポイントになります。
6.当社の口頭試験対策サポート
口頭試験対策で最も重要なのは、「本番を想定したシミュレーション(模擬面接)」をどれだけ繰り返せるかです。頭の中で答えを考えるだけではなく、実際に声に出して話し、第三者からフィードバックを受けることで、回答の内容・伝え方・表情や態度まで総合的にブラッシュアップできます。
当社では、対面だけでなく Web(オンライン)での口頭試験対策 にも対応しており、ZoomやTeamsなどのWeb会議システムを利用することで、全国どこからでも受講が可能です。仕事や移動の都合で会場まで足を運びにくい方でも、自宅や職場から効率的にトレーニングを行えます。
具体的なメニューとしては、
- 口頭試験のポイント解説付き「講習」
- 本番形式で行う「模擬面接」
- コンピテンシーの観点で答案・話し方を見直す「個別フィードバック」
を組み合わせたプログラムを、1回5,000円(税込)~ ご提供しています。受験状況やご希望に応じて、回数や内容のカスタマイズも可能です。